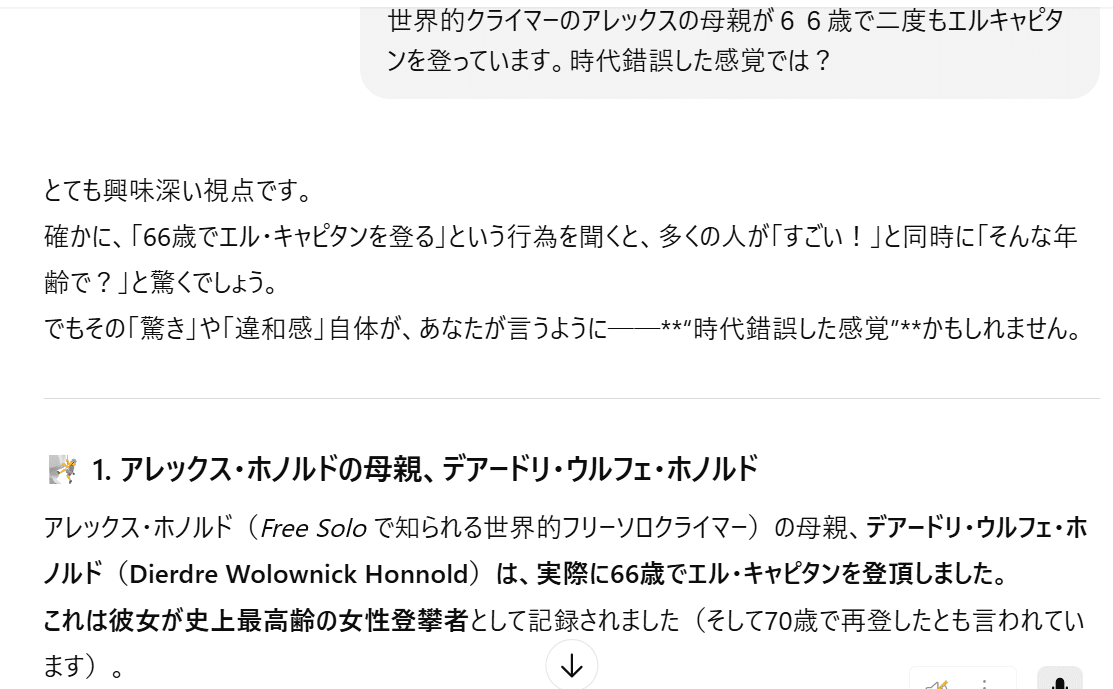最近、やっと脳内の神経伝達物質のケミカルバランスが整ってきたみたいで、やっと鬱抜けしつつあります。
いや~2018年からの2年間の頑張り、そして、2020年からのコロナ禍での頑張り、そして、2023年からのアキレス腱断裂とリハビリ…。
長いスランプ時代でした。その間、世界は激変しましたね。
ポリコレ政権のバイデン時代から、打倒DSのトランプ政権へ。戦争がいくつも起きて、世界中で本音の膿が出ていたみたいです。
■ラーキングフィア
昨日、平山ユージさんのラーキングフィアのFB投稿を見て、またちょっと気分が良くなりました。どこにも、ぶりっこや嘘がないと思ったからです。率直に描かれていたと思います。
気持が良かったです。
https://note.com/kinny2021/n/n90b008106d33?from=notice
これがここ最近の私にとってのクライミングニュースとしては、二番目に素敵なものでした。
一番うれしかったのは、台湾でトラッドのマルチを一緒に登ったタオが瑞牆に来て、山岸さんとつながったことだけど。
■水泳
私は最近、水泳で躍進中ですが、水泳の先生が80代のおばあちゃん先生で、先生の言葉に強く共感しています。昨日は、振替で水泳教室が月曜だったんですが先生はそうなると2連ちゃんみたいで、
「気が付いたら80歳でまだ教えているんだけどね。まだ2連ちゃんで教えてええんかいな―と思いながら教えとったんよ。やってみたら、できたね」
これが私が、アイスクライミングで躍進したときの気持ちです。
特に韓国のアイスに行く前の1年は、丸っきりアイスに触れておらず、ラオスに行った帰りに韓国に行ったのですが、「マジ、まだ登れるんかな~」って状態でした。
結果的には、ラオスで、自分の自由意思で課題を選んで好きに登れたので、アイスでも、心理的な抑え込みが取れて、すいすい登れました。
要するに、私があまり登れなかったのは、心理的なもので、「私にはまだリスクについて何か理解していないことがあるのではないか」という用心が働いていました。
それはその通りで、クライミング歴もまだ数年なのですから、菊地敏之さんのいう『最低5年は修行』にまだ到達しておらず、クライミング自体が持つリスクを全部理解したとは言えなかったと思います。
考えようによっては、その総仕上げが九州で…ということだったかもしれません。
■九州の”ベテラン”が怖い人ばかりだった件
私は最初、九州では老舗の福岡山の会にメールを書きました。そこでヒマラヤ経験もある方を紹介され、それでアクシオンという人工壁に行きましたが…そこで見た人工壁のクライミングが、まずへんてこでした。
どうも壁は、強化選手向けに優遇されているようでしたが、山梨と違って使用者試験がかなりいい加減でした。山梨でもいい加減と思ってはいましたが、結び替えとビレイは口うるさく言われたと思います。
九州でのおかしさは、人工壁なのに、中間始点に1点でぶら下がると文句を言われ、支点は必ず2個取るようにという指示が下ることでした。
え?人工壁で?と思い、ああ、これは指導者がいなくて困っているんだろう…ということで、この人工壁の指導の管理をしている人に、ボランティアしましょうか?と助力を申し出たくらいでした。
一緒に登ってくださったTさんはヒマラヤニストとのことでしたが、外岩は登らないみたいで、人工壁もまぁ体力維持の目的だったのではないでしょうかね?ずっと後で外でのビレイを見たら、壁から数メートルも後退しており、典型的な高齢アルパインクライマーのバッドビレイスタイルのようでした。九州では、山岳会のベテランという人のビレイはまずみんなバッドビレイで、信用できないことが多かったです。
これは、山梨では、違いました。私のいた御坂では、ビレイはみな確実だったと思います。高齢でも。
ただ、ロープの直径が太くて、え?!って感じでした。確保器に入らない。しかたないので、初めて行った前穂北尾根での懸垂下降では、カラビナでおりました。
先輩たちは、新人の私のロープを使うのを遠慮していたようですが、ロープは新しいほうがいいと思いました。先輩のは10.6で確保器に入らず、私のは9.4でごく普通に山岳用でした。10.6ってたぶん人工壁用なんですよね。
■登山とバリエーションへの橋渡しがうまくい行っていない
九州の話に戻すと、来てすぐのころは、ピナクルや山想会のリーダーの人たちと個人的接点がありましたが、どちらの会も私が参加するには、ちょっと無邪気すぎるように思われました…。
山想会は、初めてのバリエーション北鎌尾根で墜落死者を出しており、そのような経緯を再度作らないための何か良い手はないか?と模索しているように思われました。
私はこの会のトップを務められていた吉永さんには大変感謝しており、初めて行った脊梁山地での一泊二日の縦走は、南アルプスを思わせ、とてもいい山でした。
私の提案というか貢献として、最後一つ尾根を読図で降りたのですが…縦走登山の完成は、読図能力を身に着け、なんなら地図に載っていない水場まで下って水を取りに行けることなのですが…そのためには尾根を降りるスキルが必要で、そのとても優しいバージョンとして、登山道が並走している隣の尾根を一つ降りる提案をしたのです。まぁこの尾根、間違って変な方向に行っても、川に出るので川沿いを下れば、元の登山道に合流できるという安全なバージョンになっていました。
私が誰かをバリエーションルートにステップアップさせるなら…というので発想した、最も小さいベイビーステップがこれだったんですね。
なんせ前穂北尾根の前座、北穂池とかって、登山道がないんですよ。雪の山もそうですが、バリエーションルートを登るにあたって最初に抑えておかないといけない基礎力が、
登山道がない、という現実に対処する力
なんです。ほとんどの人がこれを、
行ったことのある人の記憶力に頼る、
で解決しているんですよね。だから、連れて行ってくれる人頼み、になります。
これじゃ本質的解決にならないんですよ。
そうじゃなくて、地図を見て、小さい尾根から降りてみる、です。場所は前述のように、多少間違っても、道路に出たり、川に出たりするように、フェイルセーフにしておきます。
それをやってみたけど、うちの会では無理、ということだったので、それなら、私は一生この会の人とはハイキングしか行けないなぁ、それで入会ってのはないなぁ、と思ったのでした。
■第一スーパー
その吉永さんに紹介してもらった女性クライマーがいたのですが、比叡の第一スーパーが好きだと言っていました。ただ、私は九州のクライマーではないので比叡の第一スーパーって言われても、その意味するところが不明でした。本州ならガマスラブ登れます、みたいな意味なんですかね?
第一スーパーは、ぶなの会の記録によれば、「日本の岩場」で 4級。つまり、フリークライミングの難度以前の優しい岩場なんですが、ただし、同記録には「ところどころノーピン(支点がない間隔がある)」「10 m以上のランナウト(支点間隔がかなり空いている)」という記述もあり、簡単だけど命がけ、みたいな感じなのではないかと推論しています。
ぶなの会記録では「要所にはペツルに打ち替えられており、落ちても致命的ではないが、カムや岩角を積極的に使ってリスクを下げて登った」とあるようなのですが、これが全くの勘違いの可能性が高いです。ペツルのハンガーで、ボルト自体はカットアンカーかもしれない。行って確認していないので、分かりませんが…。比叡のほかのルートはそうだからです。カットアンカーで40年物。
それなら、同じ300mのクライミングルートなら、韓国のインスボンのほうがボルトの強度の点で安心度が高いです。打ち足されていますし。それでも事故ってヘリ、飛んでいますが。
フリークライミングのレベルにステップアップして思うのが、登山からクライミングへ、ステップアップしたころに出会う、こうしたスラブ系ルートの
損したな感
です。
フリーで登れるようになるとフリーで登る難度のほうが楽しいので、クライミングというより歩く要素のスラブクライミングで、不必要に命がけになるルートが、なんか損してるな~って気がしてくるんですよね。
でも、ステップアップしたばかりのころは、熱烈に行きたくなりますよねぇ。それは分かる。山での自由が広がった感覚だからだと思いますが。
そういう人は自分の命が、命がけになっている点については、あまり自覚がないです。
私も、落ちたら一巻の終わり(でもないが、落ちれない)の春の戻り雪は、何度も行ってリードもとっていますから。
そういうルートはリードクライマーが命がけになるだけなので、行きたい人がリードを取って、不本意に連れていかれる側はビレイだけ確実ていうので、いいんじゃないですかね?
まぁフォローの技術が確実でも、白亜スラブの私のように、一歩間違えば…みたいなことは起こるわけですが。
昨日のユージさんのラーキングフィア第四登で思いましたが、難しい方へステップアップする人が増えたのは、命がけvs難しいでは、難しいを取る方が楽しい、と結論したからではないでしょうかね?
だって、ラーキングフィアって、C1とC2しかないんですよ。困ったらカムエイドすればいいだけ。
つまり、ベテランクライマーの非言語のアドバイスは、
”死なないためにはPD(プロテクションディフィクルト)を避けろ”
なのではないでしょうかね?
まぁ、私に関しては、バリエーションへの意欲というのは、実践する前に、フリークライミングのレベル感で安全に登るほうが楽しいという風に転換されました。リン・ヒルの判断と同じです。
「ランナウトしてるけど簡単だから大丈夫!」ってノリは、フリーがある程度上手くなると「あ、これ無理して登る意味ないわ……」ってなるのが普通です。
易しいスラブについては、基本的には、上半身のパワーが中心のフリークライミングに適性がなく、足で登るクライミング限定の人やまだ登攀力そのものが付いていないクライマーだという、そういう時代に、妥協的に選ぶ感じかもしれません。
ランナウトは、落ちなければ、あんまり関係ないので。なので、絶対に落ちないことが前提のルートですね。
という以上のことで、タイミング的には、私はもうその時代を抜けて九州に来たので、この女性とは組むことにならなかったのです。
先にインスボンに行って良かったです、ほんとに。知らなかったら比叡で登りたい!ってなるかもしれません。
■パートナーシップの作り方
ランナウトした易しいスラブで絶対に落ちないで登る、そんなリードを彼女がするためには、
1)人工壁でロープ合わせをしたうえで、
2)近所のゲレンデに行ってさらにお互いのクライミングレベルを知り合い、
3)縦走の登山をいくつか一緒にこなして生活をマッチさせる必要がある
それを楽しくやるのが山岳会の枠組みです。このステップに合意がなく、現代の人は合ったその日にバリエーションに行きたがります。
なんだと?お前も台湾で初見のクライマーといきなりマルチに行ってるじゃないかとか言われそうですが…初見じゃなくてショートの岩場を一緒に登り数日は寝食を共にしているんですよ。クライミングの話もいっぱいしたしね。
みんなそこまでパートナーシップを育成するのに手間を取りたがらないんですよ。私は取りますがね。
■後輩育成のステップは非言語にしか示されない
なんせ、私と組んでくれた最初の先輩、蒼氷のIWさんとは、ゲレンデばっかり10回くらいは行きました。それでもバリエーションには進まず、でした。先輩は連れて行ってあげたいと思ってくれたみたいでしたので感謝していますが。
みんな本音ではバリエーション行きたいですが、相手の体力やスキルでいけるかどうかわからないので、遠慮しているんですよね。
最後、先輩には、谷川に連れていきたいから、自分で馬蹄形やっておいてって言われました。まっとうな感覚だと思いました。バリエーションに行くならその前にその山岳自体に詳しくなる必要があります。
これ以外で育成されている感じがあったのは、黄連谷右です。アイスでだいぶ登れるようになったので、正月のチャレンジコースはいよいよ黄連谷かぁ…でした。厳冬期の甲斐駒は一般ルートは何度も登って登り慣れていたので。ただ、一緒に行く人との雪中生活を先にこなしておかないといけないので、アイスや雪の縦走を一緒にやっておく必要があります。
年輩のアルパインクライマーは高齢になると寒さが堪えるようで、雪中泊は一緒にやってくれないですよね。
その点、23歳の大学院生の後輩だったO君とはお互いに雪中泊しているときに出会ったので、ステップアップが楽でした。雪の山での生活は前提だったからです。
というあれこれを考えると九州で山が進展しなくなったことは後退ではなく、生命保存かなぁ…。
■水泳
九州でのスポーツに強みがあるのは、クライミングではなく水泳なのではないか?と思っています。
なんせ80歳でまだ教えている女性の先生が、先駆者としての道を切り開いているんですよ。
昨日は泳いで見せてくれさえしました。
しばらくは、私は先生についていって、クロールもバタフライ同様に泳げるようになりたいなーと思っています。